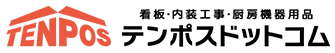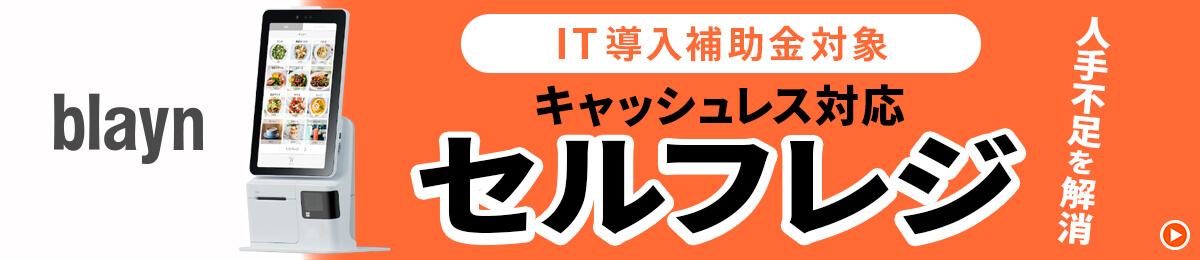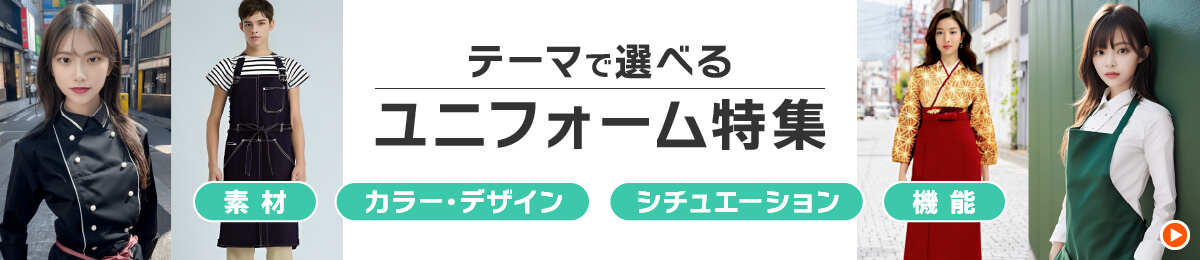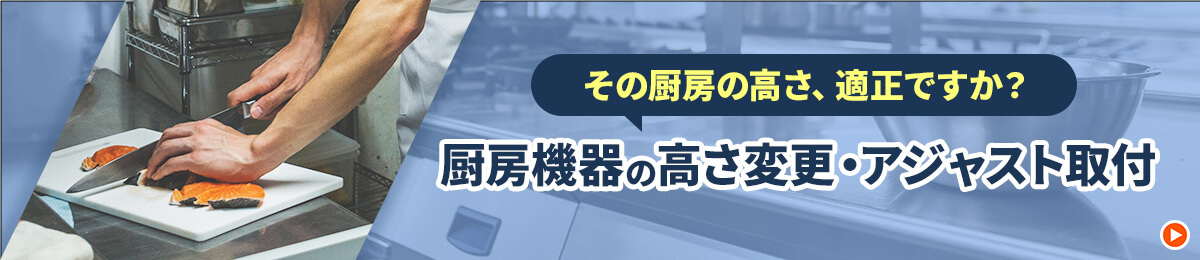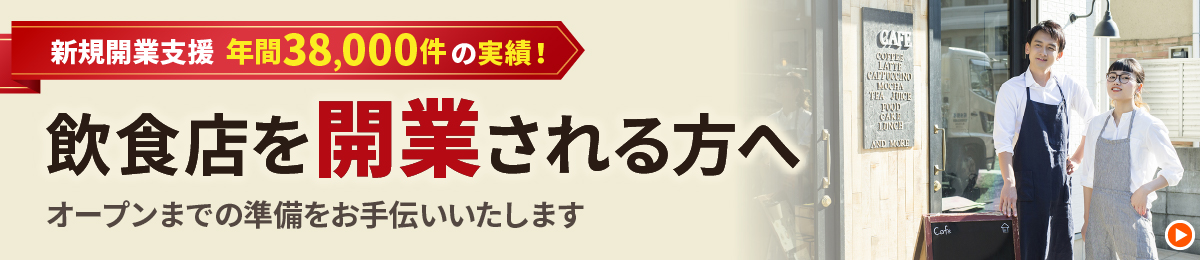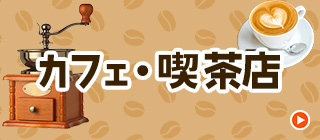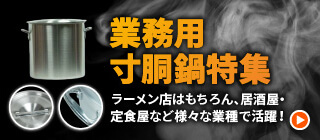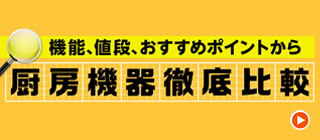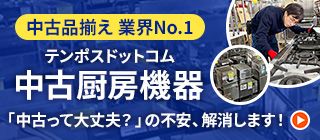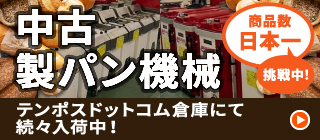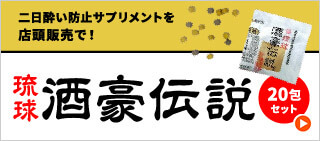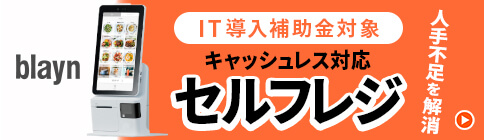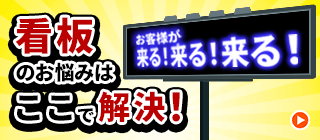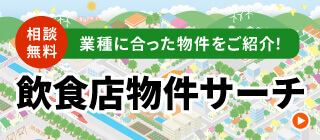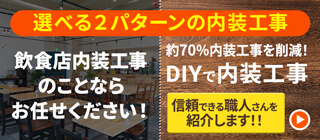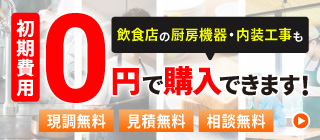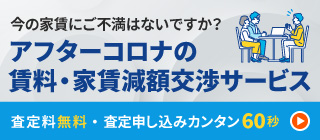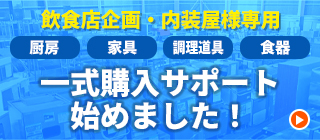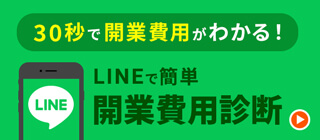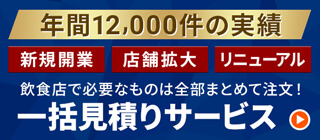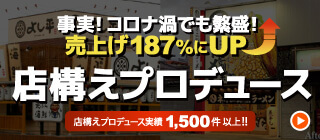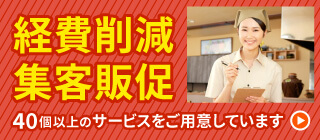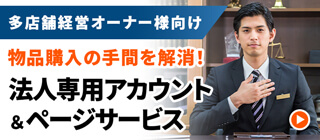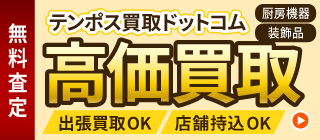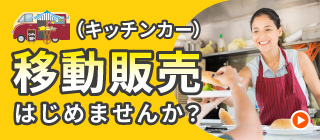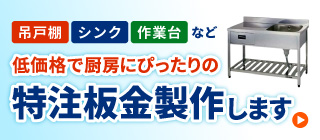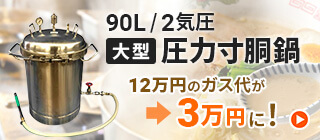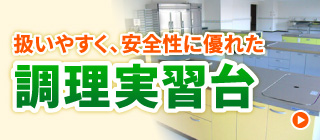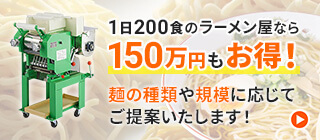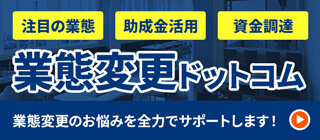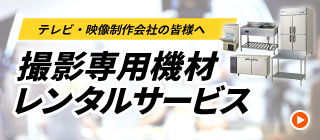累計販売台数3万台突破!
【業務用/新品】【テンポスオリジナル】冷凍ストッカー 上開きタイプ 93L TBCF-93-RH 幅574×奥行564×高さ845(mm) 単相100V【送料無料】
販売価格
¥
25,740
税込